河川工事による河川のリフレッシュ~河川環境を考慮した施工~
緑豊かな宮崎県でも 多くの森林が伐採され 進捗率日本一という林道網が構築されています。
そこからのびる 作業道や土捨て場から崩落し 一雨ごとに 濁水と土砂を河川に運びます。
運ばれた土砂は 谷を埋め 河床に堆積します。
河川工事によって 河川内の砂利をふるい20センチ以上の石を河床に戻すことで浮石状態をつくり
本来あるべき川の状態に近付けようとしています。


















宮崎県延岡土木事務所 河川課の協力によって事業の中で河川再生の取り組みがなされています。
(写真提供 有限会社 クリエイト)
実施イベントのお知らせ
~河川清掃・マスつかみ捕り大会~(毎年8月第2日曜日)
河川環境保全活動の一環として平成17年から組合員によるゴミ持ち帰り運動を行っています。
この取り組みは自分がゴミを残さないのは勿論の事、漁の行き帰り目についた空き缶・ビニール袋など持ち帰ろうとするものです。
また「川はみんなの友達」を合言葉に、一般のボランティアの方達とも一緒に河川清掃を行い、清掃終了後はみんなで川遊びをします。
大人だって遊びたい!をコンセプトに、ニジマスのつかみ捕り大会の始まりです。
水深の違った池を造り、子供から大人まで楽しめる工夫をし、楽しみながら川の素晴らしさや自然の大切さを理解して欲しいと考えています。
~鮎チョン掛け大会~(毎年8月14日)
「まつりきたがわ」に連携して北川の伝統漁法である鮎チョン掛け大会を行います。
チョン掛けとは、2m位の竹竿の先に丸針をセットして竿を手前に引き、魚を引っ掛けて獲ります。
天然鮎は動きが速くなかなか獲れないので、川の上下流1kmの間を網で仕切り、その中へ20cm~25cmの養殖鮎300kgを放します。
水中メガネを着け、群れ泳ぐ鮎を見ながら行うこの漁法は、普段は組合員のみが許された漁法ですが、年に1日だけ一般の方達も体験できるチャンスと県内外からも多くの参加者が訪れます。
体験した人達は、口々に楽しさと水の綺麗さを話し、自然のもつ魅力のとりこになります。
~ふれあい魚釣り大会~(毎年11月第1日曜日)
障がいのある方や、お年寄り、子供たちなど、普段川に接する機会の少ない人達を北川に誘い、自然に包まれて楽しい一日を過ごしていただきます。
多くの方々のご協力のもと、河川120mを5m×5mのマスに仕切り、魚釣り、つかみ捕り、チョン掛けが始まります。
並行して延岡市生活環境課による水辺の生き物調査、チームのぼり猿によるのぼる君とのジャンケン大会、アミータさんによるドラムサークルが行われ、お昼には日本赤十字延岡奉仕団による、おにぎりや豚汁、釣ったばかりの魚の串焼きなどが振舞われます。
女性ユニットAyasによる太鼓演奏、ジョイコールのべおかのゴスペルなども大会を大きく盛り上げてくれます。
第2回ふれあい魚釣り大会では、1,000名を越える参加者で賑わいました。
このイベントを通して河川環境に対する考え方、川とのふれあい方、自然との共生について、肌で感じながら学び清流北川を守るために自分達に何が出来るかを考えて頂く機会としました。
釣り竿やチョン掛け竿、串など小さな備品は全て組合員の手作りです。
また、大掛かりな池などは北川建設業協会の方々のご協力で造っていただきます。
いろいろなイベントを通して川を大切にする心を培い、水辺周辺の環境を周りの人々と共に守り甦らせる努力をしていきたいと思います。
北川漁協では、ふれあい魚釣り大会の参加者、ボランティア、出店者を随時募集しています。
参加希望の方は、下記の申込書をダウンロードして、郵送でお送りいただくか、直接北川漁業協同組合へご持参ください。
~マイストーン作戦~(毎年総会開催日)
清流であるはずの北川も、ダムの有る本流域では水量が減り、川の流れが緩くなる冬から春先にかけ、ノリや汚れが岸辺の岩や石を覆います。
鮎が最も成育する5月~6月、漁場活性化を図るために組合員やボランティアの方達にご協力をいただき、デッキブラシで石の表面を磨きます。
綺麗になった石の表面には、鮎やボウズハゼなどの好む珪藻や藍藻が生え、魚の成育を助けます。
自分達の漁場は自分で守るという気持ちを表すネーミングとしてマイストーンとしました。
このような取り組みを通して清流北川を甦らせ、多くの人たちが水辺に遊び魚釣りがしたくなるような川を残していきたいと考えています。
多様性のある雑木林の保全
平成12年より豊かな水をつくるため「水を守る森を残そうかい」を立ち上げ、水辺の環境保全の取組みを始めました。
「水を守る森を残そう会」でなく「残そうかい」に成っているのは、北川の方言で語尾に「かい」を付けると「何々を一緒にしましょう」の意味で、周りを誘う時に使います。
この取組みは、今伐採されようとしている樹齢30年以上の雑木林を切らずに残そうとするもので、植林をすると考えた時に植え付けや下草刈などの費用がかからないだけでなく、今在る多様性のある自然が残され、何よりも樹齢の分だけ時を戻せるメリットがあると考えました。
考える事は簡単ですが、形になそうとするといろいろ大変です。
まず山を残す場所の条件について河川流域であること、雑木林であること、30年以上生育した林であること、1箇所にある程度まとまっていることなど問題を提起してくれます。
場所が定まっても、所有者のご理解とご協力を取り付けなければなりません。
これが一番大変な作業でした。
10年目を迎えたこの活動も、周りの御理解をいただきながら昨年までの9年間で380.9町歩の多様性のある雑木林を保全することができました。
流域に雑木林を残すことは、水産動植物資源の保護のみならず、人間の営みにも深い関わりがあります。
自然環境保全を進め、清い流れの中に多種の魚類や水生生物があふれる豊かな川を目指し、水源の森つくりを継続しています。

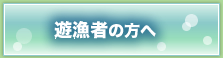
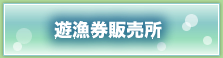
 北川漁協インスタグラム
北川漁協インスタグラム